24時間インターネットが出来ることやサービスを利用できるのは、誰かが運用や保守をして管理しているおかげ。客先常駐で運用・保守をしたときにそのことを思い知りました。
さてそんなシステムやサーバー周りの運用・保守ですが、「それらの仕事はどんなものなのか?」「どういったスキルが得られるのか?」など気になると思います。本記事ではそういった運用・保守についてまとめました。
ただ最初に結論を言うと運用・保守の仕事は最初こそ実績を作るのにおすすめですが、ずっと続けるべき仕事ではないと思っています。
運用・保守っってどんな仕事?

運用・保守とは、主にITの分野においてコンピュータシステムやネットワークシステムの正常な稼働を維持するために行われる諸種の管理作業を総称する言い方です。
24時間365日稼働が当たり前となったネットワークにおいて、システムやネットワーク・サービスのダウンタイムは、ビジネスにおける大きな損失となります。企業の規模に関わらず、ネットワークとサービスの可用性を高く保つことは重要です。
では具体的にどのような業務があるのか、解説していきます。
ping監視
別名死活監視とも言われています。ットワーク内に配置した機器やサーバー・システムが意図通りに稼働しているか、外部から監視することを指します。
具体的には、Pingコマンドを定期的に送信し、受信先の効きやサーバーが正常に稼働しているかの返答をチェックします。ただ最近はPing監視を簡単に自動化するツールも出ているため10年後も全く同じことをしているかどうかは不明です。
負荷状態監視
リソース監視とは、サーバー内のCPUやメモリの負荷状況、ハードウェアの利用状況、ディスク使用状況、などを監視します。リソースの許容量を超えてしまうとユーザーがサービスを受けることができなくなってしまうため、このような監視も必要になります。
ハードウェア監視
サーバーやネットワーク機器の物理的な故障が無いかを監視します。例えば、搭載しているCPUやメモリ、ハードディスク、電源供給装置といった部品が故障していないか、機器内の温度が異常に高温になっていないかを監視します。
アプリケーション監視
サーバーに搭載されているアプリケーションが正常に動作しているかを監視します。例えば、正常・異常のログを出力している場合は、それを監視します。
ネットワーク監視
サーバーやネットワーク機器間のネットワークに異常が無いかを監視します。通信が途切れている、混雑しているといったことが、どのネットワークで発生しているかを視覚化し、対処する機器を特定します。
運用・保守エンジニアのメリットとデメリット

「運用・保守の仕事内容」についてはなんとなく理解していだけたと思います。では実際に運用・保守をしていた感想を踏まえた上での、メリットとデメリットをまとめました。
メリット
就職しやすい(未経験や資格なしでも可)
Web系のシステムエンジニアなどの人気職と比べると、競合も少なくITスキルがなくても、就職しやすいです。
理由は末端の運用・保守要員の場合は、ひたすら目視でツールをチェックして何かあったら上司にエラーを伝える、ということが多いため、そこまで高度な技術を必要としません。
「IT系の職種にキャリアチェンジしたい」「空白期間があるけど正社員として働きたい」という人は比較的良いんじゃないかと思います。
業務実績を作りやすい
ITエンジニアのキャリアを作る上で必要な要素として、資格以外にも業務実績がというものがあります。
転職をするにおいても、常駐案件に参加するにも、過去の業務実績を記載したスキルシートが評価されます。正直な話大した業務内容でなくても、過去に触れたプログラミング言語やサーバー・OS、その他ツールの実績が多ければ多いほど評価されがちです。
運用・保守エンジニアは上述の通り、未経験や資格なしでも働きやすいので、後々の業務実績を作ることも容易です。
デメリット
スキルが身に付きにくい・エンジニアの中では末端の扱い
IT系のエンジニアというと様々な職種や業務内容があります。
- 顧客との要件を詰めて必要なシステムを設計する「コンサルタント(または上流工程エンジニア)」
- システムに必要なサーバーやネットワークなどのインフラを設計・構築する「インフラエンジニア」
- 設計した内容を元にコーディングを行う「プログラマー」
- 完成したシステムやインフラなどのテスト・デバックを行う「テスター」
などなど
開発現場の工程では、提案→設計→構築作業(プログラミングなど)→テスト→納品・導入→運用・保守にて品質を保証。というのが一般的な商流です。
開発工程の中でも下の方が運用・保守であるため、どうしても下の方の部類の扱いになります。
重要ではない部分であるため、スキルが身に付きにくく、不況や予算が赤字になったときに切られる可能性が高くなります。
シフト制や夜間業務がキツい
私も経験がありますが、運用・保守エンジニアは24時間365日交代制で働くため、心身ともにキツいです。
そのため挫折する人や、体を病んでしまう人も出てきてしまいます。Yahoo!知恵袋などでも「運用監視 辞めたい」みたいな書き込みを多数見受けられます。
スキルが身に付きにくい
不具合に対して、適切にハードやソフトの処理をできるトラブルシューターになれば、スキルもニーズもあります。
ですが、ただPingコマンドを実行したりツールを目視してエラーがあったら上司にエスカレーションするだけ、というような運用・保守エンジニアである場合スキルが全然身に付きません。
そのような仕事ばかりをしていると若いうちはいいですが、年齢を重ねたときにつぶしが効かなくなりますし、年齢に応じて単価が上がった時に仕事を貰えない可能性も出てきます。
AIにより仕事がなくなる可能性もある
エラーが起こった際にトラブルシューティングを行っているエンジニアは別ですが、ツールで状態をチェックしていたり、トラブル時のコールセンター的な業務だけしているエンジニアは今後切られる可能性がありいます。
システム開発などIT化の最大の目的は、手作業を減らし機械化することで人件費の削減を実現している流れが一般化しています。IBMのワトソン(人工知能)が某銀行でのコールセンター業務を行っているのは新聞で見たことある人もいると思います。
人工知能を導入することで、運用・保守は大幅な人員削減する流れになると感じています。
運用・保守エンジニアのキャリアプランはどうするべきか?

メリットよりもデメリットの方が目立ってしまったかもしれない運用・保守の仕事。では最初から運用・保守は外した方がいいいのかと言えばそういうワケでもありません。
運用・保守の案件は下積みと考える
私の主張は末端の作業員・連絡要員は定年までやる仕事はありません。上述でも触れた通り、運用・保守エンジニアは開発現場では末端であるためスキルアップも出来なければ切られやすいからです。
スキルが身についてない、年齢を重ねただけのエンジニアは現場でも扱いずらいですし、末端作業のエンジニアという条件であればもっと単価の安い若手エンジニアに任せればよいと、責任者は考えるでしょう。
ですが、運用・保守エンジニアは、仕事が貰いやすい案件の1つです。「未経験だけど正社員になりたい」「ITエンジニアのキャリアパスを築きたい」というのであれば、運用・保守に力を入れている会社またはそういった現場からスタートすることをおすすめします。
キャリアアップをして好待遇のエンジニアになる
最初は運用・保守案件ばかりを対応するエンジニアとして勤務するのも全然アリだと思っています。
運用・保守案件を経験して実績を積み重ねて、「基本情報技術者」や「CCNA」などの資格を取りながらキャリアアップするというプランを取るべきです。
すでに業務実績を積んだ人は転職をするべき
既に1年近くエンジニアとして勤務していて、業務の内容が辛いのであれば転職を考えるのも1つの手です。
私も運用・保守エンジニアとして現場に1年くらい常駐していましたが、スキルアップも見込めず精神的に病んでしまったため転職をしました。
元々いずれは独立してフリーランスとして活動をしたかったため、転職先もそれに合う経験が出来る企業をを選んで頂きました。
もし、現状の業務に不満や将来にい対して悩みがあるようでしたら、一度相談だけでもするべきです。
運用・保守エンジニアの転職先を紹介

私は客先常駐エンジニアをしていて、4次請けレベルの運用・保守業務をしておりました。
その後はストレスとスキルが身に付かないことを恐れて転職、エンジニアをしつつもIT営業である「セールスエンジニア」や自社のWEB担当、その後は統括する立場のWEBディレクターなど、様々な経験をすることができました。
キャリアの積み方は様々で、運用・保守をやっているのであれば、「構築SE」というキャリアが1番手が届きやすいですし、私の様にITに関する様々な仕事を広く展開して「ジェネラリスト(スペシャリストの反対)」になってもいい。
また、「エンジニア以外の働き方」や「IT業界以外のエンジニア」という選択肢もあります。
この章では運用・保守エンジニアの転職先に付いてご紹介します。
①:構築SE
ネットワークエンジニアの仕事は、ネットワークの設計から要件定義、構築、保守・監視、運用など多岐にわたりますが、大きく次の4つに分類することができます。
言い方は悪いですが、運用・保守(監視も含む)は、ネットワークエンジニアの中では「誰でもできる」「待遇が低い」ポジションです。
もし、キャリアアップを測りたい・年収を増やしたいと考えるのであれば、要件定義や構築ができる上位のネットワークエンジニアを目指すべきです。
【構築SEのメリット】
- ユーザーの感謝を一番に感じられる
- 休日や深夜の出勤、電話におびえなくていい
- 運用部隊に指示を出す立場になれる
②:ITコンサルタント
ITコンサルタントとは、ITを切り口に顧客のビジネス・経営に関わるコンサルテーションを提供する職業のことです。
SEとの違いを簡単に述べると、ITコンサルタントの仕事とは、より顧客のビジネス目標の達成に重点を置いて、経営課題解決に向けた現状分析~改善案、顧客ニーズに合ったシステムや技術を提案すること。
つまりはITを導入すれば「どれくらいの費用対効果が実現できるのか」を考え顧客に提案する仕事です。
クライアントから話を聞いて経営課題をあぶり出し、どのようなシステムを導入すればその課題を解決できるかを提案し、提案がクライアントに承認されれば、SEに「こんなシステムがほしい」と要望を伝え、システムエンジニアがその要望に沿ったシステムの開発に取り掛かります。
ITコンサルタントのほうが、システムエンジニアよりさらに上流の工程を担当する職種であるといえます。
プログラミングなどの技術的な仕事が得意でなく、かつ営業や提案することの方が得意ならば検討してみてはいかがでしょう?
③:セールスエンジニア
セールスエンジニアとは、技術的な作業を行う「エンジニア」と、顧客への提案や課題解決を行う「営業」の両方の役割を持つ仕事のことです。簡単に言えば技術営業というポジションになります。
私が、客先常駐エンジニアから最初に転職した業種です。ただ提案するだけではなく、顧客の指示をエンジニアに伝えたりなど間を取り持つ作業や、導入後のサポートなども行いました。
私の肌感覚ですが、
- 技術が分からないでごり押しで提案するだけの営業
- 技術はあるけど口下手でクライアントに報告・提案ができないエンジニア
というのは実に多いので、そこそこの技術や知識がありながら、そこそこ提案することができる広範囲にそこそこの業務ができるゼネラリストは需要があると思って転職しました。
また営業というだけあって、更なる転職・キャリアアップも狙うことができます。
- 転職・異動などにより他の製品・技術のセールスエンジニア
- セールスエンジニア以外の営業
- セールスエンジニアのマネージャー
- ITコンサルタント
など
④:社内SE
社内SEの仕事先はIT以外の業種になります。IT以外の業種では社内の情報システム部門・IT担当として社内システムの整備やトラブル対応することになります。
自社のシステム管理・運用だけでなく、社内のシステム導入やネットワーク管理やPC等のヘルプデスク的なサポート業務も担当します。
私も一時期契約社員的な立場で社内SEを経験しましたが、業務の大半はヘルプデスク的な感じの仕事で、
「エクセルでこの関数ができないから教えて」
「朝からネットの調子が悪いのでルーターの調子を見てきて」
など、エンジニアとは言い難い雑務をこなしていました。
客先常駐エンジニア同様スキルは身に付きにくいですが、社内SEを置けるだけ金がある会社であることが多いため、クビやリストラにはなりづらいと考えて良いでしょう。
また、自社でシステムの一新となれば、上流工程からシステム開発に携われるケースもあるため、他社に外注することになれば、元請け側としてのマネジメントスキルが身に付きます。
エンジニアはやりたいけど、IT以外の業種に行きたいのであれば社内SEがおすすめです。
ただこの業種は運用・保守だけのスキルだと難しく、プログラミングやディレクターとしての経験を見る企業もあります。いきなり社内SEを目指すというよりは、運用・保守エンジニア→プログラマー→社内SEとステップを挟む確率が高くなることは念頭にいれてください。
エンジニアの転職方法を具体的に解説

私は過去に、2回ほど転職活動をしており、転職活動に関してはある程度自信を持ってアドバイスすることができます。
運用・保守エンジニアだけでなく、IT業界に居る人は以下のことを念頭に置いて転職活動をすると良いでしょう。
①:転職サイトと転職エージェントはたくさん登録しよう
実際私が転職活動中にお世話になったオススメの転職エージェントをご紹介します。
キャリアアドバイザーに力を入れている、豊富なエンジニア向け案件を保有している転職エージェントはこちらになります。
転職を考えているのであれば最低1つ、できれば2,3個登録しましょう。複数登録をするメリットですがエージェントが独自に持っている求人を可能な限り紹介してもらえる点が1つと、また、様々な角度から職務経歴書や面接のアドバイスを貰うことで通過率アップにつながるからです。
※日本マーケティングリサーチ機構調べ
保有求人7000件以上のうち8割以上が年収600万円以上のハイクラス求人を用意しています。
アドバイザーのほとんどがIT知識の豊富な元エンジニアが支援してくれるので、あなたの良さを引き出してくれます。その結果、書類選考率64.6%、初回提案での内定率は90%を誇っています。
ITエンジニアの経験があり、さらなるキャリアアップ・年収アップにチャレンジしたい方におすすめです。
経験が浅いエンジニアにおすすめ「マイナビAGENT×IT」
全国の大手上場企業から人気ベンチャー企業、隠れた優良企業まで、多くの人事採用担当者との間に太いパイプを持っているのが特徴です。
レバテックキャリアがハイスキルエンジニアを得意としているのに対して、マイナビITAGENTは20代や未経験の転職サポートが得意です。
また私がシステムエンジニアからウェブマーケターに転職した際には、
など、エンジニア以外の業種にも強い、総合的な転職エージェントを利用していました。
IT以外の業界を見たいエンジニアにおすすめ①「リクルートエージェント」
応募が殺到しすぎるから、企業戦略上一般公開できない重要求人だからなど、非公開にせざるを得ない魅力的な求人に出会うことができます。
リクルートの優秀なアドバイザーが職務経歴書や履歴書の添削、志望企業への推薦など様々なサポートを行ってくれます。
IT以外の業界を見たいエンジニアにおすすめ②「doda」
あなたにマッチした求人の検索と応募が可能、職種、年齢、経験を問わず、さまざまな方に利用可能です。
専門スタッフがあなたの希望や適性にあった求人を紹介しているためIT業界内での転職はもちろんのこと、他業種を考えている人にもお役に立てるエージェントです。
また私自身は利用していませんが、いわゆる第二新卒・既卒・フリーターであれば、
が人気です。
既卒、第二新卒、大学中退、フリーターの就業を支援「JAIC」
厚生労働省委託「職業紹介優良事業者推奨事業」の職業紹介優良事業者として認定されているため、ブラック企業を徹底的に排除しています。
これから正社員でエンジニアになりたい方、エンジニアから別業種にチェンジしたい第二新卒の方は是非ご利用ください。
②:転職エージェントを利用するときの注意点
転職エージェントは、上述で紹介したような「履歴書・職務経歴書の添削」「模擬面接の実施」など転職サイトには無いサポートが魅力的です。
とは言え、どの転職エージェントが良いかと言うと怪しい部分があり、良い人材紹介会社でもハズレのエージェントに当たれば転職が失敗する可能性もあります。
そうならないためにも最低2社、可能であれば4社ほど登録して、様々な角度から転職を進めた方が良いでしょう。
③:企業研究でみるべきポイント
- 転職サイトでは当たりの会社とハズレの会社の違いが分からない
- 転職エージェントの場合、ちゃんとした所であればブラック企業を紹介することはないけど、ハズレエージェントの場合クソ求人を紹介してくる可能性がある
そのため転職活動をする自分自身でもある程度、企業研究を行う必要があると考えています。企業を見るポイントとしては、
- 口コミ・評判サイトで検索する
- 設立が10年以上かどうか(リーマンショックより以前かどうか)
- 事業規模(資本金や従業員数など)
いろいろな口コミ・評判サイトがありますが、私は「転職会議」を利用していました。
不満があって辞めている方がストレス発散のために書き込んでいるという属性があるため、基本的に口コミサイトというのは、ネガティブな声が多くなりがちです。(そもそも現職で会社に満足している人は書き込みません。
そのため話半分で見るべきですが、「残業時間があまりにも多い」「評価が2.5を下回っている」「有給消化率があまりにも低い」「平均年収」の4つを見て判断していました。(場合によっては口コミの内容も検討)
また設立年数は、
- 会社の約8割近くが10年以内に倒産する
- リーマンショックを耐え抜くだけ事業がしっかりしていた
という観点を判断基準に10年前後経営している&リーマンショック以前に設立されていたかを見ていました。
最後に事業規模ですが、事業規模があまりにもしょぼい会社(ドベンチャーさスタートアップ)はブラック率が高いと考えて避けました。
というのもそれらの会社は、創業者のモチベーションやビジョンなど意識は高いけど、一般従業員になる私が彼らとそれを共有できる気がしなかったからです。
彼らは借金をして目的があって創業したから意識が高くて当然ですけど、別に年収が増えるわけでもない一般従業員が彼らと同じモチベーションで働けるワケではありません。(よほどその人らや事業に共感したというなら話は別ですが・・・・
創業間もなく意識だけ高いドベンチャーよりも、50人以上の社員が居てある程度組織が回り始めた中堅規模以上の会社に入社した方が安全だと判断しました。
まとめ
- 運用・保守は参画しやすいため、下積みにはなる
- ただスキルは身に付きにくい・夜勤などがあるためいつまでもする仕事ではない
- 転職先は結構ある
- 今すぐにでも転職エージェントに登録して準備をしよう
私自身、運用・保守をしているときは深夜業務に心身ともにダメージを受けていました。(+αで下請として客先常駐をしていたので上位会社からのパワハラも相当ありました)
耐えきれなくなって転職をしたのですが、おかげさまでいろいろな経験を積むことができ30歳で年収500万円を貰い、一時的とはいえフリーランスとして働くスキルも身に着けました。
今後のキャリアについて不安があるあなたは、まず転職エージェントに登録して、エージェントのカウンセリングを受けてみましょう。公式サイトへのリンクを貼っておきます。






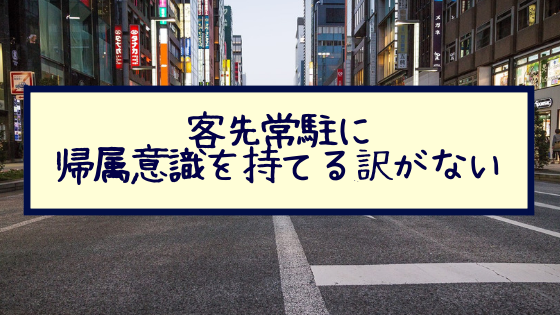

コメント